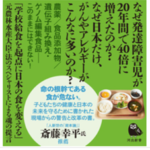第83回 コンビニ弁当やロレックスの時計は果たして不要か?
こんにちは、小島正美です。前回(第82回)、経済思想家の斎藤幸平氏(東京大学准教授)が、山田正彦・元農水大臣の本の推薦文を取り下げたというお話を載せましたが、その後、山田氏の本「子どもを壊す食の闇」の紹介がネットから削除されていること ...
第82回 山田正彦氏の本に対して、あの斎藤幸平氏が推薦文を取り下げ!
こんにちは、小島正美です。経済思想家の斎藤幸平氏(東京大学准教授)といえば、ベストセラー『人新世の「資本論」』の著者として、マスコミで売れっ子の学者なのは、みなさんもご存じの通りです。その斎藤氏が、元農水大臣の山田正彦氏の本の推薦文を ...
第80回 ついに出た検証記事「おいおい鈴木君」の大特集
こんにちは、小島正美です。世の中にはデマや偽情報も含め、さまざまなニュースや記事が出回っていますが、それらに対して一つひとつ、真偽を確かめ、どこが間違っているかを検証することは至難の業です。学際的な専門知識が必要なだけでなく、とてつも ...
第66回 地球温暖化原因論争は科学的な事実を争うレベルで勝負してほしい
こんにちは、小島正美です。
通常は食の安全や健康問題などに関する話題を書いていますが、今回は番外編です。温暖化で本当に災害が増えているのか、気候変動の将来予測はどの程度確かなのかをめぐる論争です。この問題に関して、国立環境研究 ...
第65回 週刊誌は、いつから消費者の味方をやめたのか
こんにちは、小島正美です。
消費者庁が3月末、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表した。その狙いは、消費者に誤認を与える無添加・不使用表示にストップをかけるためだ。言い換えると消費者がだまされないための警告シグ ...
第64回 ゲノム編集食品の普及を阻む要因は本当に“不安解消”なのだろうか?
こんにちは、小島正美です。日経産業新聞(6月10日付)の一面トップにゲノム編集食品に関する記事が大きな扱いで掲載された。ゲノム編集食品は日本が世界の最先端を走るだけに、今後、日本で伸びていくためには何がネック(阻害要因)になるのだろう ...
第63回 ゲノム編集食品に対する記事はなぜ「偏り」が生じやすいのか?
こんにちは、小島正美です。
ゲノム編集食品の開発では、日本が世界の最先端を走るが、気がかりなのは市民団体による反対運動だ。いまゲノム編集フグをめぐって、京都府宮津市が反対運動に揺れている。メディアの報道いかんによっては、国産の ...
第56回 マスコミが作り上げた虚構が、いつの間にか心理学の定説に?
こんにちは、小島正美です。今回は、本の紹介も兼ね、「食」の世界にも多いに関係のあるジャーナリストのあるべき使命について考えてみます。その本とは、オランダ出身の若きジャーナリスト、ルトガー・ブレグマン氏(1988年生まれ)が著した「希望 ...
第49回 「緑茶は農薬まみれ」の記事に、お茶業界はファクトチェックで対抗すべき
こんにちは、小島正美です。予定を変え、前回に続いて週刊現代の「日本茶は農薬まみれ」(6月5日号)の記事に関して考えてみます。週刊誌の威力はかつてほど強くはないでしょうが、そうはいっても、茶葉やお茶のペットボトル飲料が「農薬まみれ」と書 ...
第47回 緊急続報!大学入学共通テスト・英語の人工甘味料問題 ~あの「赤本」に注釈が入った
こんにちは、小島正美です。今回は、大学入学共通テストの英語の問題で、人工甘味料(もしくは低カロリー甘味料)が危険かのような記述がされて波紋呼んだ、という第41回の記事()の緊急続報です。共通テストの載った「赤本」(教学社)が出版された ...